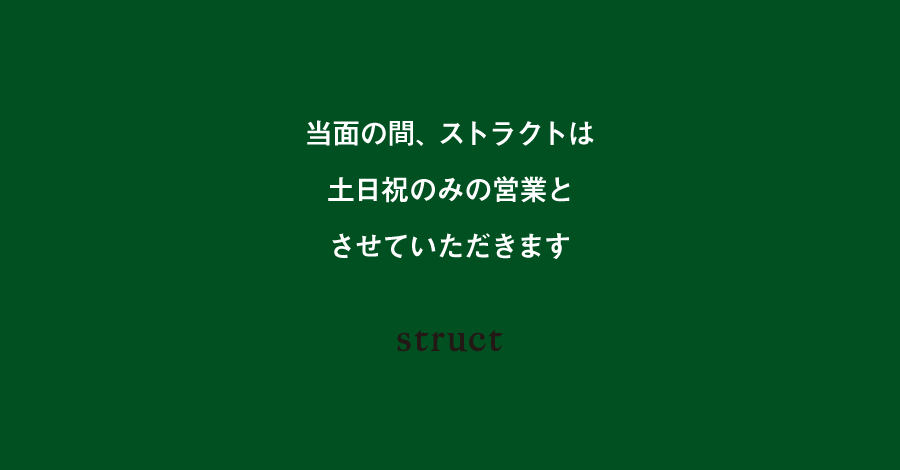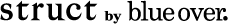イマイズミの、blueoverによせて。 -vol.1-

ストラクトへ来てはや1ヶ月半。 私イマイズミは改めて考えることがある。
私が福岡からわざわざ大阪まで足を運んでblueoverのスニーカーを買いに行き、今こうしてスタッフとして売り手になったのは、もちろんblueoverのプロダクトそのものに惹かれたからだ。
では、どこに惹かれたのだろうか?
「日本製のスニーカー」「どんなスタイルにも合うデザイン」「快適な履き心地」
blueoverの商品説明では、こういう謳い文句が並べられている。
確かにその通りだ。
私自身、接客の際には同じ言葉を使ってお客様にお伝えすることがある。
では、これらのフレーズに惹かれて、私はblueoverに興味を持ったのだろうか?
いや、きっと違う。
わかりやすい魅力があるのはもちろんだけれど、スニーカーに足を入れるその前から、私はblueoverに惹かれていた。
プロダクトの本質的な、感性に直接訴えかけてくるメッセージ。
blueoverの真髄のようなものを、私はスニーカーの姿の奥に、確かに感じ、そこに惹かれたのだ。
では、そのメッセージとはなんだろう?真髄とはなんだろう?
店頭に立って、商品の知識を仕入れても、なかなかその答えは見つからない。
だとすれば、blueoverの本質に最も近い人物に聞くのが手っ取り早い。
blueoverを立ち上げた渡利ヒトシさん(以後:渡利)に『blueoverについて話を聞きたい』と告げると、彼は快く対談に応じてくれた。

渡利 ヒトシ
blueover デザイナー
モノを作ってきた人達への恩返し
「まずは、自分の経歴から話そうかな」
卒業後はデザイン事務所に就職し、その後フリーのデザイナーとしていろいろな企業と家電製品やスポーツ用品の企画・開発を行ってきた渡利。
プロダクトデザイナーとしてモノづくりに携わっていく中で、日本の製造業の衰退を目の当たりにしてきたという。
2000年代は、多くの企業が海外生産にシフトし、そのピークを迎えつつあった頃だ。
一方、かつてはその高い技術で素晴らしい製品を生み出してきた国内の工場や職人は、阪神大震災からリーマンショックを経て、続々と廃業が増えていた。
80〜90年代、モノを所有することに価値観を見出していた『モノを消費する時代』を過ごしてきた渡利。
「今の自分を形作ってくれた、モノを作ってきた人たちに貢献したいというか、何かできることはないかっていうのを考えました」
渡利が出した答えは、小さな規模でもいいから、継続的に国内で製造ができる状況作りをすることだった。
「そこには多分、育ててくれた親への恩返しのような気持ちもありました。」
そうした思いから、渡利はいちプロダクトデザイナーとして、作り手と協力し仲間たちとブランドを始めることを決意する。
では、なぜスニーカーを作ろうと思ったのか?

blueover≠スニーカーブランド
「じゃあどのようなプロダクトを作ろうかって考えた時、真っ先に浮かんだのがスニーカーだったね。」
青春時代をスニーカーブームの真っ只中で過ごしてきた渡利にとって、スニーカーという選択は最も自然で、エネルギーを注ぐには申し分のないプロダクトだ。
「でも、少し語弊があるかもしれないけど」
と前置きをして渡利は言う。
「blueoverは”スニーカーブランド”。というだけではないということ。」
意外な発言に驚いたが、続く言葉で納得した。
「ブランドの目的は、あくまでも国内のモノづくり業界への貢献。」
と渡利は力強く語る。
blueoverは、これまで渡利が携わってきた仕事・人・工場といった繋がりと、自身がスニーカーが好きだった事、今渡利がやることの意味を繋げ合わせた結果、出た答えだった。
「でも当時は本当に理解を得ないところからのスタートだったよ。個人のデザイナーが『ブランドをしたいです』って突然やってきて、業界のことも何もわかっていないから、トンチンカンなことを平気で口にした。本当に今思うと恥ずかしい行動だった」
と渡利は振り返る。
生産数も当然最小。
「正直、工場からしたら何も旨味のない仕事だったと思う」
いろいろな人に苦言を言われ、その無謀さに飽きられることも多々あった。
それでもしつこく町工場を回るうちに、少しづつ理解を示してくれる方たちが現れ、協力してくれるようになっていった。
「うれしかったよ。自分の考えに協力してくれる人たちは、同じようなモノつくりへの想いがあり、同時にこれからへの危機感を抱いていたように思う。」
もちろん、デザイナーと現場とで考え方の相違もある。
意見が衝突したこともあった。
しかしそれは、お互いモノが好きで、熱い気持ちを持ってモノづくりに向き合っていたからこそ生まれた軋轢。
それは、渡利自身がよくわかっている。
「モノづくりをやっている人は、作り上げることが本当に好きだと思う。私もそう。 その気持ちがあるだけで、どんな衝突があっても、困難な壁があっても解決しようとする気持ちが生まれる。」
デザイナー、工場の職人など、関わる人々がそれぞれ”良いモノ”とは何かを本気で考え抜く。
「そこに生まれる意見の相違は、心地の良い軋轢であり、しっかりと話し合うことで必ず良い結果が生まれると信じている。」
なるほど、と私は頷く。
どうやら勘違いをしていたようだ。
シンプルなデザインで歩きやすい国産スニーカーを作ることこそ、blueoverの存在意義だと思い込んでいた。
けれど、スニーカー作りは、モノづくり業界への貢献という目的を果たすために、渡利が選んだ手段だった。
その手段を通じて、渡利はもちろん、工場の方々、職人らが『良いモノ』を追求し、衝突し、本当の意味での信頼関係を築き、生まれたのがblueoverだった。
**************
私は、ふと考えた。
『目的と手段はときに入れ替わってしまう』
社会人になった時、最初の研修でそんな話を聞かされたことを覚えている。
今、私は『目的と手段』の区別を意識して仕事に取り組めているだろうか。
目の前の手段をこなすことに精一杯になってはいないだろうか。
では、私がstructで果たすべき目的とはなんだろう?
**************
渡利の話を聞く中で、彼がblueoverを通して果たそうとしている目的を知り、blueoverの真髄に一歩近づいた気がする。
とはいえ、私がblueoverのスニーカーに感じた魅力は、モノづくり業界への恩返しという目的に起因するのだろうか?
さすがにスニーカーを一目見て無意識に
“おぉ、このスニーカーには何かよくわからないけれど、熱い使命が宿っているな”
などと鋭い察知まではしていないはずだ。
目で見てわかる部分に何か引っかかるものを感じたに違いない。
続いて私は、スニーカーの見た目に直結してくるであろう、渡利のデザイン思考について尋ねた。
vol.2につづく…

関連記事
No related posts.